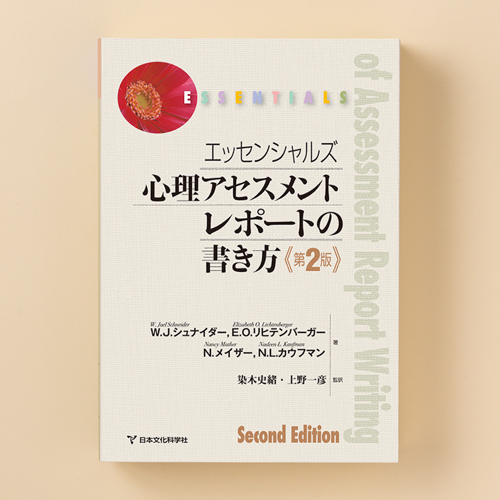石隈利紀先生に聞く
ウェクスラー知能検査の倫理と使用者の責任
第4回 心理検査の実施・活用に際しての倫理と責任:
結果のフィードバック(フィードバック面接・所見作成)
2025.07.29 インタビュー / シリーズ
検査の実施に携わる具体的な場面における倫理と責任について、ラポール形成・検査の実施・結果のフィードバックという3つの場面を軸に順に話を伺っております。
-- 前回は検査の実施についてお話しをお伺いしました。最終回となる今回は、検査実施後に行う結果のフィードバックについてのお話しをお願いします
石隈 はい。それではまず、なぜアセスメントを行うかについて思い出してみましょう。インタビューの冒頭でも話しましたが、アセスメントとは、発達障害などで苦戦したり生きづらさを感じていたりしている方々が何かしらの援助を受けるという場面で、心理職など援助者がその方の状況を理解して、適切な援助案のための資料を作成することです。援助を受ける方の特性やニーズにあわせて援助者や環境が変わるのです。その為にアセスメントは必要であり、援助の基盤となるものなのです。
-- WISCやWAISなどの心理検査も、そのために実施するということでしたね
石隈 そうです。そして、実施した心理検査を援助に活かすために必要となるのが、結果のフィードバック、つまり結果の解釈と報告です。
-- 結果のフィードバックにおける留意点を教えてください
石隈 結果のフィードバックに際しての倫理・責務として、2つのことを意識してください。まず1つは、検査を受けた当事者(以下、「本人」)が、発達の特徴について理解することを支援することです。本人が自分について理解を深めるということはとても大切なことです。2つめは、検査を受けた本人にかかわる方に、検査結果を支援に活かしてもらうことです。本人の自己理解と、本人にかかわる方への適切な支援案づくりが、アセスメントの目的になります。もちろん支援案づくりは、本人と相談しながら、協働で進めます。
-- では、フィードバックは具体的にはどのような方法で行うのでしょうか
石隈 フィードバック面接という形で直接話をする、所見作成という形で文書を作成するということが考えられます。どちらかではなく併用することが多いですね。フィードバック面接、所見作成ともに、本人に対して直接行うもの、保護者などの非専門家に対して行うもの、それから専門家同士で共有するものなどがあります。
-- フィードバック面接に際して、気をつけるポイントはありますか
石隈 検査を受けた本人とのフィードバック面接では、本人が「主語」で、わかりやすく端的に伝えるよう心掛けてください。相手の反応を確認しながら話すことも忘れないでください。 例えばWISC-Vを受けた子どもに、「こういう特徴(凸凹)があったよ」ということを話して、本人にピンとくるとか、こないとかという意見を聞いて、「どんなことが援助としてあなたの役に立つかな?」とか、「このように私は思っているんだけどどうかな?」など、結果についてやりとりをする時間を持つことです。このような時間はとても大事です。
-- 検査を受けた本人が自分についての理解を深める、ということですね
石隈 そうです。ただ、残念なことに教育センターや病院などで、本人へのフィードバック面接の時間を十分にもつことは、現実問題としてなかなか難しいとの話をよく聞きます。日本公認心理師協会や公認心理師の会など職能団体では、フィードバック面接の時間確保に向けて、医科診療報酬としてフィードバック面接が認められるよう働きかけています。
-- 現実的にはフィードバック面接の時間確保という問題があるのですね。
それでは次に、所見作成に際して、気をつけるポイントを教えてください
石隈 アメリカでの大学院生時代に「個別知能検査とケースレポート」という授業を通して、Alan S.Kaufman先生(以下、「アラン先生」)より所見作成についての指導を受けました。その中で強く印象に残っていることがあります。10歳の男の子のWISC-Rの結果について、「言語関連の得点が弱かったので、幼児期の教育環境・養育環境がよくなかったのだろう」ということを書きました。このレポートに対してのアラン先生からの問いかけは、「あなたはこの子の幼児期を見たことがあるのか?」「この報告を読んだ親はどう思う?」「ちゃんと説明できるか?」ということでした。
-- アラン先生は何故このようなことをおっしゃったのでしょうか
石隈 アラン先生は、この問いかけから「エビデンスがないことを勝手に書いてはいけない」「読み手に配慮する」という2つの大切なことを教えてくださいました。まずは、背景情報や行動観察といったエビデンスに基づいた解釈と報告をするということです。そして、相手に失礼にならないように、相手が嫌な思いをしないよう読み手に配慮するということです。検査結果のフィードバックは、相手へのエンパワーメントの機会なのです。面接でも同じことが言えますよね。
-- 結果を伝えるに際し、忘れてはならない心構えをアラン先生は教えてくださったのですね
ではここからは、所見に記載する内容について、詳しいお話しをお願いします
石隈 まずは、検査の目的・主訴です。本人の訴え、本人からすれば今困っていること、解決したい問題ということです。それから、背景情報ですね。本人の日ごろの様子や発達史を保護者の方などに教えていただいて書きます。既往歴なども必要に応じて書いてください。
-- アラン先生がおっしゃっていたエビデンスの収集ですね
石隈 そうです。そして次が実施した検査の結果です。検査中の取り組みの様子など、検査者から見た行動観察も重要なエビデンスとなりますから忘れずに書いてください。さらに検査は1個だけではなく、検査バッテリーといいますが、複数行った場合は、その検査から分かったことについても報告します。文書によるフィードバックでも、もちろん主語は本人です。
石隈 続いて検査結果の解釈です。解釈は、背景情報と行動観察に基づいて行ってください。大事なことは、読み手が、検査を受けた方の知的な発達の特徴を理解できる内容にすることです。心理検査ではありませんが、例えば、我々が人間ドックを受けた際、検査結果の細かい数値の説明だけでは理解できず、「この結果をどう受けとめたらいいの?」と不安に思ってしまうことがありますよね。
-- 確かに、不安に感じた経験があります
石隈 そうなんです。心理検査についても同じです。特に、本人や保護者といった非専門家の方に対して結果の説明を細かく行うことは、かえって混乱を招くかもしれませんので気をつけてください。WISC-Vなどの知能検査や面接といったアセスメントの結果をまとめていく場合、得点だけを示すのではなく、本人を主語にして、例えば認知能力(視空間能力・記憶など)・学力(読み書きなど)・社会性と情動などの領域ごとに、このような場面で高い能力を発揮したとか、こういうところが苦手だったなど、わかりやすく書いてください。
石隈 さらに、結果の説明ということについてですが、検査の内容が流出しないように気をつけてください。非専門家の方に対しては、下位検査あるいは項目についてはお示ししないほうがいいと思っています。検査の内容が流出すると標準化された心理検査の価値が下がってしまいます。これは、苦戦している方が適切な検査を受ける機会を奪うことになります。
-- 検査の妥当性を保つために留意すべきことですね
石隈 はい。そして、最終的には、結果の解釈を踏まえた援助の提案も書きます。「だからどうしたらいいの?」についてです。例えば、どんな特徴があって、特にどんな強いところが勉強に活かせるかなどの提案を具体的に書いてください。本人に対しては、図とか絵とか使った方が分かりやすいからもっと使おうとか、保護者や教師など支援する立場の方に対しては、そういうものをもっと使いましょうということなどを示すことです。
-- 所見には、検査の目的・主訴から援助の提案に至るまで様々な情報が必要なのですね。結果のフィードバックを学ぶに際して、何か良い参考書はありますか
石隈 「エッセンシャルズ 心理アセスメントレポートの書き方 第2版」がお勧めです。私は第1版からの大ファンで、1版ではアラン先生も共著者です。2版は代わってNadeen L.Kaufman先生が共著者になっています。そして上野一彦先生が両方監訳にかかわっていらっしゃいます。大学院での授業や、現場の先生方の研修会などでも是非活用していただきたい1冊です。
石隈 検査の実施の際にもお話ししましたが、結果のフィードバックも積み重ねが必要です。検査をきちんと実施できること、支援に活かされる結果のフィードバックを行うことは、心理職の責任です。心理検査に携わるための能力というのは極めて重いということを心に留めておいてください。
-- 4回にわたって心理検査にかかわるとても大切なお話を、先生のアメリカでのご経験談などを交えてわかりやすくお話しくださりありがとうございます
石隈 最後に私が座右の銘としている、アラン先生の言葉をお伝えしたいと思います。
「知能検査は、子どもの学力を予想し、安楽椅子に座ってその悪い予想(子どもの失敗)が当たるのを待つために実施するのではない。アセスメントで得られた情報(得意な認知スタイルや望ましい学習環境等)を子どもの援助に活かすことで、その予想を覆すためにある」
まさに文部科学省が2022年に示した『生徒指導提要』にもあるように、子どもの支援は、子どもの個性の発見とよさや可能性の伸長を支援することにあるのです。
石隈 利紀 先生
東京成徳大学応用心理学部・大学院心理学研究科特任教授 筑波大学名誉教授
日本公認心理師協会副会長 日本学校心理学会理事長 学校心理士認定運営機構会長
日本版WISC-V刊行委員会 日本版WAIS-IV刊行委員会